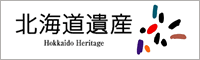湯浅拓幸
合気技の無名性と型稽古について
大東流 無博塾 三段昇段審査 論文湯浅拓幸
無傳塾に入門以来早くも7年の月日が経とうとしている。本当に月日の経つのは早いものである。その間、700回ほど稽古した。それは常に「型稽古」であった。そして、この頃、無博塾の本領は型稽古にこそあると実感している。
入門当初は塾長が稽古の際に「あれやって」とか「この技を稽古しよう」とか言われるのを聞いて、正直なところ、
少林寺拳法においては、「技法の体系」として技が「柔法」と「剛法」の二系統に分類され、それが更に幾つかの「拳系」に整然と組織されている。少林寺の拳士は六百数十とも言われるそれらの技を、入門時に全員に配付される「科目表」(と名付けられた冊子)に従って、順次一つ一つ稽古し身につけて行く。勿論全ての技に名前が付けられている。技をイメージさせるかなり具体的な名前である。そして、明瞭に示された基準(稽古回数、経過月数、指定された技の修得)に従って、師匠の推薦により、何人かの審査員の下で実技と論文の昇級・昇段審査を受け、その双方が基準点数を満たした者が合格とされる。実に組織的且つ合理的であると同時に極めて有効な稽古方法であると思う。何よりも、稽古する者にとって「自分の技がどこまで進んでいるのか」が分かり易く、向上意欲を持ちやすいのが特徴である。私は、こうした稽古方法は勿論のこと、その根底に流れる禅思想の面でもその技の面でも少林寺拳法は極めて優れた武道であると今も思っている。
一方
大東流における有名無名のあの技やこの技は、その技を使えること自体が目的なのではない。あの技やこの技が使えるようになることを通して、究極の「合気」を身につけることこそが最終の目標なのである。究極の到達点なのである。そこに到達した時、それぞれの技に名前は要らない。敢えて言えば「合気」という名のただ一つの「技」がそこに存在するだけである。その境地を目指して、我々大東流を稽古する者は日夜型稽古を繰り返し、修行に励むのである。「何もしない」とは、「あの技やこの技をしない」ということなのではなかろうか。「ただ黙って背筋を伸ばし、姿勢を正して真っ直ぐにそこに立つ、座る。」「ただゆったりと静かに息を吐き、吸う。」「全身のカを抜いてただ相手の前に立つ、相手のカを受け容れる。」それは通常の武道の概念からすれば到底「技」とは言えない。しかし、我々無傳塾の目指す技はまさしく「これ」なのであり「あれ」なのであり「あの技」に他ならぬのである。
「合気」とは一体何か。まだ僅か7年しか修行していない私にそれはわからぬ。或いは永久にわからぬかもしれぬ。しかし、それは感じることができる。人聞の体と心との玄妙不可思議な働きとしか言うことのできぬものとして確かにある。自分が手を開く時、相手が崩れて行く。少なくともその時に「合気」はその姿を垣間見せる。この「手を開く」ことこそが型稽古の出発点であり、到達点である。或いは、その全てであると言っても過言ではあるまい。
この「技」への道のりは余りに遠く、余りに長い。しかし、到達点は恐らくある。見えている。そして、型稽古のみがこの「技」に、「合気」という名の「唯一の技」に到達するただ一つの道なのではなかろうか。型稽古とは、謂わぱ、「一つ一つの技」という「個物」を通して「合気」という「普遍」に至り着く為の唯一最高の道なのではなかろうか。我々は、それを信じて、一歩一歩修行して行くしかない。私は、嘗て明暗尺八と少林寺拳法の修行を通して、「量が質に転換する」ということを学んだ。「千回の稽古」ということの意味を教えられた。先ずは「千回の稽古」を目指して、地道に気長に
修行
(平成27年5月23日)