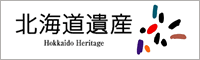合氣ロード
会津で生れ北海道で育った大東流合氣柔術(合気道の源流)
世界の武道人口のランキングは1位が空手、次に柔道そして3番手が合気道である。
このように広く世界に流布している合気道のルーツが「大東流合氣柔術」なのである。
我が国武道の殿堂である「日本武道館」に於いて毎年行われている「日本古武道演武大会」にエントリーされている古流武術である。
大東流合氣柔術中興の祖・武田惣角翁は門人を前にし
「ほうら、簡単だろう。だから見せないのさ」と言った。
自然な姿勢とゆっくりとした呼吸。そして、触れたら即技――。何もしないことから始めて生まれる合氣技法は老若男女を問わず、全ての武道修行者が追求できる生涯の道となる。
武田惣角から手解きを受けた門人は明治、大正、昭和の三代に亘り多士済々であり大正14年竹下勇海軍大将、昭和9年岡田啓介総理大臣等には “試される大地” ここ北海道から出向いて指導している。
明治36年(1903)米国より初のプロレスラーが来日、仙台警察署において2名が惣角と試合をし惣角に完敗した。
当時、米国より派遣され来日していた英語教師チャールス・ア・パリーは帰国してルーズベルト大統領に報告して知るところとなり同大統領の要請により惣角の代理として原田信蔵を派遣渡米させ普及している。
現在プロレスの技には大東流合氣柔術の技が相当使用されているが往時米国で指導を受けたレスラーが、その道の者に伝授し、今日に伝えられたものと思われる。
北海道との係わりは明治43年(1910)当時秋田県警察部長、財部實秀が北海道警察部長に栄転の際、要請により随行渡道したのが始まりである。
札幌では4年程指導していたが、札幌で食べた帆立がとても美味しく、産地ならなおさら美味しいであろうとわざわざ湧別まで帆立を食べに来た折り堀川幸道の父(村議会議員、渋川流柔術の免許皆伝、駅逓堀川旅館を経営)泰宗と運命的な出会いがあった。
泰宗は是非その秘術を授けてほしいと懇願し武田惣角は15年余の流浪の旅に終止符をうち永住を決意させたのであった。
大正2年堀川泰宗、大正3年息子幸道(小、中学校長歴任、昭和49年永世名人位の称号を授かる)そして大正4年植芝盛平(白滝在住)は遠軽で入門、後年東京に転出して合気道を創始し国内外に流布した。
また惣角の長子である時宗は大東流合氣柔術の宗家として網走に在住し国内外に普及活動を展開したのである。
地図で 合氣ロード を表示
この大東流は会津(藩の御留技、殿中護身武芸御式内)を出て、”試される大地” 北海道で育ち神秘の武術或いは大和心の武道と称せられ、日本の北海道の無形文化財であると自負し国内外への指導普及に努めているところである。
著名な門人を列挙してみる。西郷従道(元帥陸海軍大臣隆盛の弟)山崎興造(旭川、銘酒男山社長)佐川幸義(湧別)吉田幸太郎(湧別)川島栄三郎(日本銀行小樽支店長)横山昌次郎(北海道銀行取締役)松田敏美(旭川、弟子の奥山龍峰「八光流を開く」)坂東幸太郎(国会議員、旭川市長)俵孫一(北海道長官、商工大臣)前菊太郎(旭川)細野恒次郎(東京近藤勝之入門)久琢磨(大阪琢磨会)山本角義(苫小牧)無限神刀流居合術創始等が各地におり多士済々、各氏の門下より幾多の優秀な門人が輩出し「合気道の源流」として大東流も合気道共々世界的に名声を博している。
北海道から発信し、唯一現存し活躍している古流の武術こそ大東流に他ならない。
我ら合氣の武術を修行する者にとって網走、湧別、遠軽、白滝、旭川と続く一筋の道は謂わば「合氣ロード」とも呼ばれる尊い道であり、合氣の先人達が日夜修行に明け暮れたこれらの地域をこそ「合氣の聖域」と言うも決して過言ではあるまい。
不滅の合氣 三十回忌 永世名人 堀川幸道先生に捧ぐ
序章 口上
「何もしない」、これが無傳塾(うち)の技・・・
「何もしない」、これが無傳塾(うち)の流儀・・・
「何もしない」、そこにこそ合氣がある、
「不滅の合氣」がある
ただ真っ直ぐに立つ、正しく座る、それが技
ただ姿勢を正して、ゆったりと息を吸う、息を吐く、それが技
立つは技 触れれば合氣 無傳塾
先師武田惣角翁曰く、
「ほうら、簡単だろう。だから見せないのさ。」
そこに一体何があるのか。何が隠されているのか。
時には「幻の武術」と呼ばれ、時には「日本武道の精華」とも
「日本古武道の究極」とも称される、この大東流とは一体如何なるものなのか。そうして、その大東流の秘奥たる合氣とは・・・
今年、平成二十二年(二〇一〇年)は、大東流合氣柔術無傳塾開塾十周年の記念すべき年。そうして、奇しくも、大東流合氣柔術中興の祖武田惣角翁生誕百五十周年、渡道百周年の記念すべき年。
大東流とは「日出づる国」の武術。日本は世界の東の果て、極東。
北海道は日本の東の果て、そうして、網走は北海道の東の果て・・・
ここ北海道こそは近代大東流発祥の地。大東流合氣の原点。
合氣の聖地・・・
不思議な縁(えにし)、見えざる因縁の糸が感じられてならぬ。
明治四十三年(一九一〇年)、武田惣角、時の秋田県警察部長財部実秀の北海道警察部長としての赴任に際し、財部に随行、北海道に渡る。
大正二年(一九一三年)のある日、惣角は突如、飄然として湧別 の駅逓にやって来た。湧別へ来て稽古を付けてくれるよう、予てより懇願はしていたものの、よもや本当に訪ねて来ようとは思っていなかった堀川泰宗(堀川幸道の父)は驚き、狂喜した。
堀川泰宗と武田惣角翁との出会い。これこそが、正に大東流と北海道との宿命の出会いであった。
惣角翁が、湧別にて大東流を教授し始めた時、近代大東流はその産声を上げた。そうして、この嬰児(みどりご)は、多くの育ての親達に見守られながら、先ずは同じ北海道の地、遠軽、白滝へと歩みを記し、伝播し、大きく逞しく育って行った。
大正二年(一九一三年)、湧別にて、堀川泰宗入門。ここ北海道の地が、近代大東流の一大源流となる。
大正三年(一九一四年)、下湧別にて、堀川幸道(明治二十七年〜昭和五十五年)入門。後に永世名人となり、数多の弟子を育て上げ、合氣の正統・本流として大東流合氣柔術の伝統を今日に伝える。
大正四年(一九一五年)、遠軽にて、植芝盛平入門。後に合気道を創始し、世界各地へ広める。
その他、後に合氣の技を、日本全国、世界各国へと伝える数多くの弟子達が入門。その数、およそ三万と言われる。
永世名人堀川幸道先生は、大東流合氣柔術無傳塾塾長飯田宏雄の師匠である。武田惣角から堀川幸道、飯田へと脈々と受け継がれて来たこの合氣の技こそが、大東流合氣の正統・本流であり、文字通り「不滅の合氣」と称すべきものである。
我ら合氣の武術を修行する者にとって、網走、湧別、遠軽、白滝、旭川と続く一筋の道は、謂わば、「合氣ロード」とも呼ばるべき尊い道であり、合氣の先人達が日夜修行に明け暮れたこれらの地域をこそ、「合氣の聖域」と言うも決して過言ではあるまい。 誓って
我ら合氣の正統を受け継がん
合氣の道に精進せん
合氣の修行に励まん
合氣の見えざる糸によって結ばれ、
「不滅の合氣」に導かれ・・・
The Eternal Aiki of Kodo Horikawa Meijin.
“Do nothing.”
This contains the essence of the techniques of Daito Ryu Muden Juku.
“There is nothing.” This is the essential transmission of Muden Juku.
“It is nothing.” This is true Aiki.
What then, of techinique?
Technique consists of standing perfectly straight, or sitting upright, and, when one’s posture is correct, inhaling quietly, then exhaling.
Using this technique when standing, Aiki exists upon touch.
There is no source.
Nothing comes from without.
Sokaku Takeda Sensei said:
“You see, this is really simple, so, you should not show this.”
So what is “this” that is obscured?
Sometimes, it is referred to as “The Phantom of Martial Arts.”
It is both “The Flower of Japanese Budo.”
And
“The Origin of the Classical Martial Traditions.”
Whatever this is, it also lies at the heart of Daito Ryu Aikijujutsu.
The inner mystery of Daito Ryu is “Aiki”…
This year, 2010, marks the tenth anniversary of the founding of the Muden Juku.
It also is the 150th anniversary of the birth of Sokaku Takeda, the Art’s reviver, along with being 100 years since the Art’s first public dissemination.
Daito Ryu is an art from “The Land of the Rising Sun.”
Japan is seen as being positioned in the far east of the world.
The island of Hokkaido is located in the east of Japan, and the city of Abashiri is located in the far east of Hokkaido.
This city was the base of modern Daito Ryu, the source.
“A Twist of Fate.”
In 1910, Sokaku went to Hokkaido, the northernmost island of Japan. He accompanied Takarabe Sanehide , who had been appointed chief of the Hokkaido police, from Akita in Northern Japan, in the role of a bodyguard.
One day, in 1913, Sokaku arrived a the fishng village of Yubetsu.
He took a room at an inn ran by Taiso Horikawa, Kodo Horikawa’as Father.
Taiso was of Samurai lineage and was trained in Shibukawa Ryu jujutsu and recognised Sokaku’s level. He beaceme Sokaku’s student and thus, Daito Ryu began to be disseminated in Hokkaido.
Sokaku was invited to Yubetsu to teach by Taiso and Daito Ryu was born in its modern incarnation. This fragile incarnation was nurtured by many “parents” who practiced the Art as it spread to many other places in the Area such as Engaru and Shirataki.
Taiso became Sokaku’s student in 1913, in Yubetsu city.
The following year his son, Kodo joined the Ryu in Shimo Yubetsu
After this, for the rest of his life, Horikawa Meijin devoted himself learning and transmitting the true art and correct Aiki to his students who have carried his teachings on to today.
Morihei Ueshiba started to learn the Art in 1915. From this humble beginning, he developed the Art of Aikido which has spread across the world.
The art of Daito Ryu was admired by Martial Arts afficiandos throughout Japan. Up to 30,000 people practiced the Art and most are recorded in Sokaku’s recored books called “eimeiroku”
Due to Sokaku’s unceasing effort,relentless travelling, frmidable skills and indomitable will, the foundation of modern Daito Ryu was firmly laid across Hokkaido, including Hakodate, Sapporo, Iwamizawa and Asahikawa.
Along with this, Horikawa Meijin received the transmission of Sokaku’s “Eternal Aiki” over many years of practice and transmitted this principle to his own students.It is this principle that Hiroo Iida wishes to transmit to his students in Muden Juku.
This principle has been transmitted dierectly from Sokaku to Horikawa to Iida, indiluted and authentic.
We who follow the bujutsu of Aiki are followed a path clearde by our predessor’s unceasing efforts, day and night. From Yubetsu to Shirataki, Engaru and beyond so that
Hokkaido may truly be referred to as “The birthplace of Aiki”.
We resolve
To pass on the pure Aiki that we receive undiluted.
To follow its path without deviation.
To develop it without compromise.
This is the invisible thread that links each practicioner on the way of “Eternal Aiki.”
The Muden Juku flag’s meaning.
The name Daito Ryu (大東流) well suits the Art’s image as a Bujutsu (Martial Art) hailing from “The Land of the Rising Sun”.* The rising sun is represented as a red circle on the Japanese flag: the “Hinomaru”.
The circle represents the eternal Universe. The red represents the energy that flows from the sun.
*Translator’s note:
When written in Japanese characters, the word “Daito” is made up of two characters. The first: “Dai” 大 means great.
The second “Tou” 東 means “East” ie: The direction from where the sun rises.
日本武道外交史に学ぶ
無傳塾塾長 飯田宏雄
2008年・平成20年8月8日から24日まで北京オリンピックが開催された。
世界が中国を知り、中国も世界を知る。
国際オリンピック委員会(IOC)のロゲ会長は五輪は中国の政治社会の扉を世界に開いた。
今年5月に来日した中国の胡錦濤国家主席が福原愛と卓球をした。胡主席は大きく振りかぶってスマッシュを披露し、見守る日本の福田首相もたじろいだようだった。
日中国交正常化の一年前、1971年春の卓球世界選手権名古屋大会に、文化大革命の影響で国際社会から孤立していた中国が参加、スポーツの表舞台に復帰を果たした。大会中に中国側が米国選手団に本国招待の意向を伝え、大会後に実現した。
米中国交樹立の足がかりとなった。”ピンポン外交”周恩来さんは中国の政治にうまく卓球を取り得た。
講道館四天王の山下、米国に渡る
日本のお家芸である柔道は石井選手が百キロ超級で金メダルを獲り面目躍如たるものがあった。
1902年・明治35年5月、講道館の高弟である山下義韶(よしつぐ・当時七段、後に十段)が北米合衆国大北鉄道社長にして世に鉄道王と称せられるサミュル・ヒルの招聘に応じ渡米し明治40年6月まで滞在してルーズベルト大統領をはじめハーバード大学、アナポリス海軍兵学校及び外交官、貴婦人団体等に柔道を教授したことが、米国に於ける講道館柔道鼓吹の端緒であるのみならず山下の大成功はやがて海外に於ける日本柔道の声価を重からしめ、柔道は続々として欧米に進出するに至ったのである。
1904年・明治37年3月9日、大統領セオドア・ルーズベルトが入門。
慶応の教授で米国に行った柴田一能が鉄道王サミュル・ヒルと懇意になり鉄道王は平生深く家庭教育に心を用い、殊に女の体育に注意していて、体格強化には日本の柔道が大に功があることを聞いていたので柴田に相談し、柴田はその人物技術を熟知した山下を推薦した。
山下は当初唯だ鉄道王の家庭教師として渡航したのであり、大統領の教師となるのは想定外の大成功だったのである。山下渡米の時、歳38。筆子夫人は12歳下の26歳であった。
米国の貴婦人たちと柔道
鉄道王のヒル夫人が、柔道の稽古を危険がって、子女に課することを望まなかったが、南北戦争で有名なるリー将軍の孫娘が勇敢にも柔道修行を思い立ち、同じ貴婦人社会の名物なる”ホース・レディー”と異名をとった愛馬家ワーズ・ウォース夫人が乗り出してきてこの夫人が大いに斡旋して、有数の貴婦人令嬢を誘って山下の教授を受けることになった。
北米合衆国はさすが女の国、その柔道鼓吹は女から始まるのである。
かくの如く、山下に肩を入れることになっては社交界は動かざるえない。山下の為に、日本固有の武道の仕来りに倣って入門帳を作ることになり、革表装の豪華な入門帳が出来上がった。この記念すべき世界的入門帳の最初の署名者は1903年11月21日第6番まで悉く婦人である。その第七番の署名者が(Blow WordsWorth)三十六即ち”ホース・レディー”で、翌1904年の2月5日は、ワーズ・ウォース夫人36歳と自署している。
この”ホース・レディー”夫妻が時の大統領ルーズベルトと極く懇意の間柄だったので、夫人から山下夫妻を大統領に紹介し、ついに大統領を誘って入門せしめたのであるから、我が柔道の海外進展を記するにあたっては”ホース・レディー”の名を特筆しなければならない。
大統領ルーズベルトの入門は1904年・明治37年3月9日にして(Theodore Roosevelt)45と自署している。
我が国に武道の入門帳多しといえどもこの入門帳こそ未曽有の国際的なものにして苟くも世界大国の皇帝又は大統領が入門帳に署名したものは古今東西ともにこの一冊より外には無い。我が柔道の世界的宝物にして珍重すべき入門帳である。
当初貴婦人たちが稽古を始めたとき、婦人の相手には婦人教師でなければならないというので、筆子夫人が急に稽古を始めることになった。
夫人は主として「柔の形」を学び山下が受を、夫人が取をやって、形通り山下を投げたのである。アメリカの新聞などは柔道の形というものを知らないから「山下は強いが、更に夫人は山下よりも強く容易に山下を投げる」などと書きたてたものであった。
大東流史と明治期の世界情勢
1903年・明治36年、米国より初のプロレスラーが来日。仙台警察署において二名が武田惣角と試合をして惣角に完敗し、その門下に入り合気柔術の指導を受け帰米したが、その後このことがルーズベルト大統領の知るところとなり、同大統領から惣角先生に対して渡米指導方の要請を受けた。
そこで惣角の高弟で当時仙台警察署武道教師をしていた原田信蔵を教授代理として派遣させ、米国各地で大東流合気柔術を指導せしめた。現在プロレスラーの技には大東流合気柔術の技が相当使用されているが、この頃米国で指導を受けたレスラーが、その道の者に伝授し、今日に伝えられたものと思われるのである。
北海道には1910年・明治43年、当時秋田県警察部長(現在の県警本部長)財部秀実が北海道警察部長に栄転の際、要請により随行来道(*2010年は武田惣角渡道百年と生誕百五十年になる。そして無傳塾十周年迎える記念すべき年)。爾来、惣角は北海道を拠点として政財官界および軍部へ大東流を伝播した。
日露戦役講和の立役者ルーズベルト大統領
1905年・明治38年5月28日の朝、山下いつもの通りホワイトハウスに柔道の教授に行くと、大統領は近づいて来て、山下の耳に口をつけて「プロフェッサ・ヤマシタ、バンザーイ、バンザーイ)と囁いた。
山下は何のことか分からなかったが、日本海の大捷であったことが間もなく分かった。日本公使館よりも、大統領の方が先にこの情報を手にしていたのである。
1905年5月27日から28日、日露戦争での対馬海峡におけるバルチック艦隊に壊滅的打撃を与えた。当時戦争能力が限界にきていた日本政府は、この海戦の勝利を機会に北米合衆国大統領セオドア・ルーズベルトに戦争の調停を依頼し、ポーツマス講和を実現させた。1905年・明治38年9月。
最初、山下が大統領から招かれて謁見するとき、日本公使館では大に驚き、竹下勇海軍大将(当時公使館付武官、大佐)を同伴せしめ、爾来両人の間には密接な連絡があった。竹下は兵学校のむかしより山下の指南を受けて熟知の間柄であったのである。
山下の外交上に貢献した功は決して少なくなかった。金鵄勲章に値すると竹下はいった。
このように中国のピンポン外交、そして日本の柔道は平和外交に寄与すること大であった。
大東流Aikiで武道外交を推進せよ!
さて、我合気は第二の柔道(大東流と合気道)と称することが出来ると考えています。
前述のごとく、柔道普及の歴史に学ぶこと多である。
小生もかつてドイツ(故米澤師範に随行、感謝しご冥福を祈る)に武者修業の折、ドイツのベルリン大使館にご招待(晩餐フルコース付)されて行ったことがあり、いい思い出となりました。
今の子供たちは将来成人して世界へ飛翔。そして男性はいずれリタイヤしてシニアとして、ご婦人たちもこのAikiの御殿術(御式内)を以って前述の筆子夫人の如くされんことを期待しております。
世界平和に貢献できる人になって頂くことを大いに希望します。
「奥義!触れ即合氣」口上文より
明治31年(1898年)5月12日、今から114年前のこと。
会津士族武田惣角源正義は旧会津藩主の松平容保の臨席のもと元筆頭家老の西郷頼母(保科近悳)から藩外不出の御留流であった殿中武芸護身術「御式内」(大東流合気柔術の中核)の相伝印可を授与された。
その折、容保からは旧会津藩において恩賞として高録の藩士に与えられていた紫の羽織紐が惣角に下賜された。また、西郷頼母近悳からは
「 知るや人 川の流れを打てばとて 水に跡あるものならなくに 」
という和歌一首が贈られた。
戊辰戦争に敗れ朝敵の汚名を着せられた会津藩は、何を思い惣角に何を託したのであろうか。
まずは、この汚名を返上すべく旧藩主は「会津藩秘伝の平法」を世に知らしめ、会津武士の威信回復を切望していたのであろう。つまり、惣角は“藩命”として身命を賭して「大東流合気柔術」の全国指導普及の行脚を始めたのである。
さて、朝敵の汚名返上の好機が到来した。昭和3年(1928年)9月28日、松平容保の四男で外交官を務めた松平恒雄の長女である節子と秩父宮雍仁(やすひと)親王(昭和天皇の弟)の御成婚である。
孝明天皇の信頼を得ながら明治維新で朝敵とされた容保公は節子にとって祖父にあたる。戊辰戦争では白虎隊の悲劇を生み、藩士らも流罪に等しい労苦を強いられただけに旧藩主の孫娘の皇室入りに地元は「会津の復権」に沸いた。幼名は節子であったが大正天皇の皇后である貞明皇后の旧名は九条節子(くじょうさだこ)であり同じ字では恐れ多いため、御成婚により会津の“津”をとって「勢津子」と改名された。勢津子妃は、父恒雄の任地であったイギリスのロンドンで生まれ、日英協会名誉総裁。秩父宮雍仁親王はオックスフォード大学に学び、英国とは浅からぬ縁があった。
明治36年(1903年)、米国からプロレスラーが来日、仙台警察署において2名が惣角に試合を挑み完敗した。当時、米国より派遣され来日していた英語教師チャールズ・ア・バリーは、帰国してセオドア・ルーズベルト大統領に報告して知るところとなり、大統領の要請により惣角の代理として原田信蔵を派遣渡米させ普及している。
大東流中興の祖である武田惣角から手解きを受けた門人は明治・大正・昭和の三代にわたり多士済々であり、大正14年に竹下勇海軍大将、昭和9年に岡田啓介総理大臣らには「試される大地・北海道」から惣角が指導に出向いている。こうして蒔かれた合気の種が芽を出して、百余年を経て大東流合気柔術を源流とする合気道は広く世界に流布、日本を代表する伝統文化の一つとして開花したのである。
今日、世界における武道人口のランキング上位は、1位が空手、次いで柔道、そして3番手が大東流を源流とする合気道と続いている。
北海道における会津藩ゆかりの地として、会津藩祖の保科正之公を土津霊神(ハニツレイシン)として祭祀する琴似神社が札幌市郊外に鎮座している。正之公は徳川二代将軍秀忠の側室の子にして、四代将軍家綱の輔佐役(大政参与)、異母兄である三代将軍家光から松平姓と葵紋の使用を認められていた名君である。明治初年より多くの旧会津藩士たちが士族移民として北海道開拓に尽力している。
もともと御式内(合気の原典)の宗師家は会津藩主が代々これを継承しており、大東流も合気道も同じ伝承系譜から輩出されたものである。
日本古来の精神の武術「大和心の武道」ともいえる大東流は偉大なる無形文化財と言っても過言ではない。
かつて会津藩の所領であった福島県は明治維新による戊辰戦争の屈辱に加え、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の苦難に見舞われている。福島県民の皆さんには、このような大いなる無形文化財を育んだことに誇りを持っていただきたい。
この未曽有の大震災により人々の絆を強めている昨今において大東流と合気道の斯界もこれを機に各流会派の独自性と特色を尊重しつつ、それぞれが謙虚になり和合の道を見出して互いの絆を強めるべきではないだろうか。
会津で代々培ってきた大東流合気の花、その花を武田惣角は北海道に根付かせた。日本全国さらに世界へとその花の種は蒔かれ「大和心の武道」の花となって咲き始めている。それぞれが手を取り合い強い絆のもと、日本の素晴らしいこの文化遺産を世界に向けて発信していきたい。
(敬称略)
世界とつながり絆を強めよう!
平成24年(2012年)3月11日