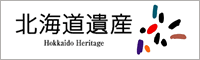南出憲宏
無傳塾は本物の合気を知るための場所(型稽古について)
無傳塾では型を通して深遠なる合気の体づくりをしている。型稽古は決して実戦のひな型ではない。即物的な強さを求めるものでもない。従って、この理解なしに合気を知ることはできない。
型稽古というと、取と受という関係の中で、取は技をかける方(後の先なので攻撃される方)で、受は技をかけられる方(攻撃する方)という単純な解釈をされやすいが、そうではない。取と受が、全身全霊で自分自身を型に落とし込み、今までの自分が経験をしていない感覚を感じ取り、取と受が互いに感覚の薄皮を一枚一枚剥ぎ取っていく作業なのである。そのため、取はどうしても相手をやっつけてやろうと技をかけることに終始し、それに対し受は取の攻撃にやられまいと頑張ることでは決してないのである。
実際の攻防においては、目まぐるしく状況が変化する中で、一瞬でも掴まれた部分に固執すれば、居着きを生み、自身の体は隙だらけとなり、敵の攻撃に晒されることになる。型稽古は実戦のひな型ではないものの、その認識を踏まえた上で型稽古に臨まなければならない。例えば、型稽古における受は、取の腕を掴み、取がその腕をある方向へ動かそうとしているがそれを押さえつけ、取の腕を動けなくさせることや単純に取の動きに迎合して動くことが正しい受け方であると勘違いしてはならないということである。取の動きが柔術か、合気かの精緻に差があっても、受は常に体感覚を鋭敏にして、取が動く時に取の微細な感覚を感じとり、取の崩しがなくなれば、いつでも動くことができる状態になっていることが重要なのである。また、取はその受の反応を感じ、自身が正しく動くことができているのかを検証するのである。(無傳塾では型で投げ型で受けよという言葉がある)
しかし、型稽古を実戦のひな型として捉えてしまえば、勝ち負けや相対的なスピード、筋力による起こりのある発動の域を出ることなく、身勝手な稽古を繰り返すのみで、いつまでも合気の極みに到達することはできない。自身の体と脳が経験をしたことがない感覚を呼び覚まし、動きの質的転換を行うには自分自身の素直さが求められてくる。だから、合気を修得するときに自分の今までの経験や考え方が邪魔になるのである。子供や女性の方が合気の技が上手であることに合点がいく。
飯田先生が指導してくださることを、自分の浅はかな考えで捉えるのではなく、純粋に受け入れ、ただひたすら型に自分自身を落とし込み、稽古を続けることによりはじめて新しい発見ができるのである。その積み重ねの先に、合気があり、実戦にも対応しうる心と体がいつの間にか出来上がるものなのかもしれない。
最後に、合気は見ただけで決して理解できるものではない。無傳塾には合気を修得するための方法論がある。堀川幸道翁の合気を求め、真摯に修行を続け、合気を体得するための術は何たるかを知り、その方法論・稽古法を含めた塾風を守り続けている飯田先生に畏敬の念を強く感じる。何故なら、この塾風なくして合気の体得はありえないのだから。
2015年11月25日
弐段 南出憲宏