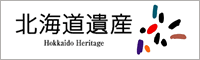布施陽菜
型稽古が教えてくれるもの
私が大東流無傳塾に入ったきっかけは海外旅行で外に出た時のことでした。自分が何も日本を理解していないと痛烈に感じたからでした。
それも現地の方と自国について語った訳でもなく、ただ日本の外に出た、とゆうだけで。
渦中にいると何事も中々見えにくいものがあります。
ただ一歩、自分と思っている境界線から出るだけで、見えるものはその意味や深さを変え「何も知らなかった」と気付けるのかも知れない。そして初めて「知る」ことが出来る。
新しい何かを知り理解しようとする時、思わず自分の中にある知識と照らし合わせ、「そうゆう事か~(わかったぞ!すでに知っているアレと同じ事だな!)」としてしまうと理解できた気がするけれど、その実今までと違う使い回しが増えたぐらいで何も得ていないものです。ではどうしたら新しい事を知れるのか。
それを体験で、実生活に活きるように教えてくれたのが型稽古でした。型稽古があるのは武術に限った事ではありません。これは廃(すた)れつつある日本伝統の物事や人間関係全般に対する“学び方”“関わり方”だと考えています。日本は他国の文化を自分のものに昇華融合するのが上手いと言われます。日本が明治維新~戦前、その勢いにも“らしさ”を損なわずに諸外国の技術や文化を取り入れられたのはこのお蔭だったのではないでしょうか。
「学ぶ」は「真似ぶ」とも言われます。型稽古はまさにそれで、今やり続ける意味が分からなくともひたすら真似て真似て少しずつ自分の中に型が出来てきます。そうしながら型に習い倣(なら)う。知らないものをそのままに手を加えず自分の中に受け入れ熟成させていくと、「型」は自分の人生の経験に応じて深さを増し、その意味を教えてくれます。この意味を自得できる喜びは本当に言葉にならない程です。
違う考えや価値観を自分に招き入れる事は、今までの価値観や生き方を壊すことではなく豊かにすることだと知識ではなく経験としてわからせてくれたのです。
そして優れた「型」は物差しとなり、自分が理から離れてはいないかを見つめる手立てにもなってくれます。
大東流は受け手も型で技を受けますが、動きが決まっていればともすれば“技がかかったフリ”の馴れ合いになると危惧されがちです。しかしそれは目の前に立ってくれている現実の相手に向き合っているのではなく、脳内の仮想の相手の動きに対応しているに過ぎません。これが時代を遡り生死のかかった局面だったらどうでしょう。本当の相手を視ていないとしたら?
人間関係も同じことで、人と会話する時、自分の中に残るものは自分の解釈か、それとも相手の話か。残るのが自分の解釈なら相手とではなく自分と会話している事になります。思い込みの世界から抜け出し「相手の話を聴く」事が出来た時に初めて関係性が結べたと言えるのではないか。そう気づけるようになりました。
そして心と身体の関係も教えてくました。稽古をするうち初めに感動したのは、力がぶつかって思うように身体が動かせない時と上手く行く時の違いは何かと考えた時、技術的な面ではないですが、上手くいく時は何も思考しておらず ダメな時は相手を倒そうとしていて、言いかえれば相手の状態(状況)を無理やり自分に合わせて動かそうとしている時は上手くいかないのです。
相手は変えられない、変えられるのは自分だけと精神的なことではよく言われますが、身体でも全く同じ法則なのかと分かった時でした。心(思考)であっても身体(行動)であっても相手を変えようとすると必ず衝突する。
しかしこれではまだ頭の中の世界。実生活で活かす為には身体(現実)に落とし込む必要があります。
その為にも稽古稽古。自分が行動レベルで変わる事を楽しみながら続けて行きたいと思います。
場を創り教えてくれる師匠にも、それに付き合ってくれる仲間にも、型を伝え続けてくれた先人にも感謝です。新たな一歩を踏めた自分が嬉しくて歩みは一生止められそうにありません。
改めて考えると当たり前に思えますが、心と身体は同じ人。心を可視化させたものが身体だと言っても過言ではないくらいで、身体を見つめることは心を見つめることと同義なのだと思います。
弐段 布施陽菜