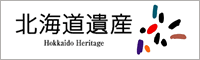合気を理解する上で大事なこと

「合気」の概念には様々な解釈があるが、本当の意味で合気を理解している者は少ないのではないだろうか。
武術における攻防の基本は、相手と同調し(相手の中に入り)相手の力をとる「崩し」の技法である。柔術であれば、力によって相手の関節や重心を攻めるが、合気は、筋力ではなく、理の中にある心身において発現される力によって相手の中心そのものを攻めて、相手を自分とつなげてしまうことである。相手の体が自分の体と一体化し、相手の体が自分の体の一部となっているので、相手を簡単に処することができるのである。但し、この合気の技法が成立するための前提条件がある。それは相手が本当の攻撃をしようとする意識の発動があったとき、また本当の攻撃をしようとした身体に対し「合気の崩し」が成立するのである。私は入門当初これを理解することができなかった。自分では本気で攻撃し、本気で掴みにいったりするのだが、明確に崩されるという感覚が得られなかった。合気なんていうのはまやかしではないかと当初疑ったこともあった。しかし、1回1回の稽古を大事に、自分自身に問題があるのではと自分と向き合う日々が続き、ひたすら稽古を積み重ねてきたある時、ふっと猛烈に合気が自分の体の中に入り、自身の力はとられ、つま先立ちにされ、何もわからず真下へ叩きつけられ、そのあとも意図せず先生の体の近くへ体がふっつき、体が硬直し、エビぞりになって固められてしまったのである。この時、如何に自分が本気で攻撃しようとし、頭では理解し、実践しているつもりでも、心身がそうなっていないことに気づいていなかったのだ。
武田惣角翁は相手をおこらせることにより、一時的に自然に相手の本気を誘発させ、合気の技をかけたという。その理屈がわかる気がする。あの時の自身の感覚は今でも忘れない。今までの攻撃は手先のみ。また無意識に技の予測をしており、当てる部分・攻撃する部分のみに集中され居ついて固まっていた。しかし、合気で崩されたとき、自分の体感覚は攻撃していく時にみぞおちは楽で、正中線の感覚も消えず、体全体がまとまって、足裏まで気持ちが下りていた。また、自分の攻撃が最初から最後までひたすらひたすらという感覚で、余計な思考が介在しないで集中しており、その状態で先生の中心へ入っていく感覚で向かっていったときに合気が入ってきたのだ。
ある部分だけおさえつけようとか、ここを攻撃しようと頭で考えながら本気でやったとしても、それでは自身の心身が理から離れてしまっており、その状態でいくら攻撃を強くし、大きくしたとしても、それは隙だらけであり、自分が居ついていることに気づきにくい。よく、ためしに合気をかけてくれと、腕をつかんでやってみろというが、中心線は折れ、部分だけ押さえつけ、探ろうと待ち構え、体が硬直し、技を予測し、その場で固まっているような相手にいくら、合気をかけようとしてもかかるわけがないし、かける必要もないのである。崩しの技法が変わってくるのだ。そんな相手には簡単に当身も入る。本気になっているつもりの本人は自分が合気の世界(本当の攻防・本当のやりとりの世界)の土俵にすら上がれていないことに気づいていないのである。
今までの自分が経験したことのない感覚を知ることであるため、理解できないままでよいし、うまくできないままでよい。ただ、一つ一つの受けをしっかりとって、一瞬一瞬を大事に、自分と向き合い、徹底的に稽古を継続することが、「本当の攻撃とは何か?合気とは何か?」を知ることができる唯一の近道なのである。
2016年10月29日
南 出 憲 宏
塾長のコメント
大東流無傳の合氣はこのような稽古の中から生まれます。
取と受の双方が共に質を高める稽古を仕合うことが最も重要なことであります。
無傳塾の稽古スタイルは輪番掛け合い方式でやっております。初心者の素直さと上級者の上手(うま)さとが融合
したものになります。
こうして無傳塾の技は標準化を図っております。
これが無傳塾の強みのひとつになっております。
大東流無傳塾 塾長 最高師範 飯 田 宏 雄